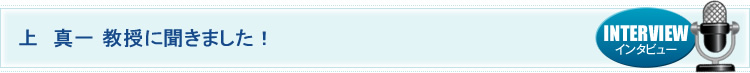 |
||||||
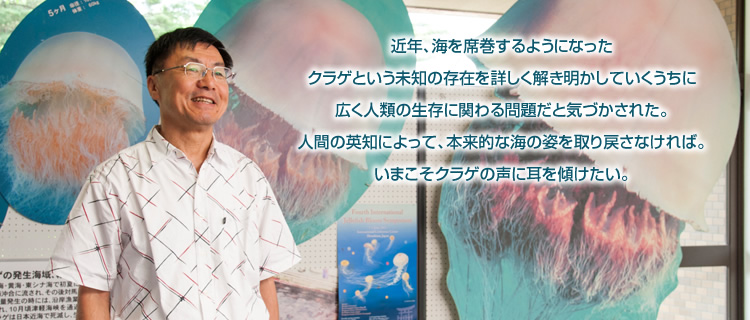 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| 上 真一 教授 | ||||||
|
ウエ シンイチ 国立大学法人 広島大学 海洋生態系評価論研究室 教授
1973年 広島大学水畜産学部水産学科卒業 2012年8月30日掲載 |
||||||
| 脚注
|
||||||
| 1. | 「海洋立国推進功労者表彰」(首相官邸ホームページ) |
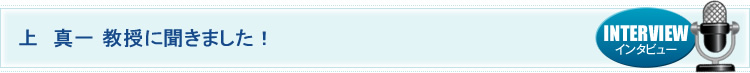 |
||||||
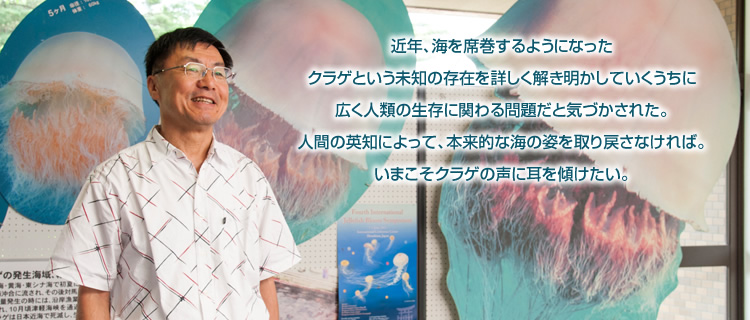 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| 上 真一 教授 | ||||||
|
ウエ シンイチ 国立大学法人 広島大学 海洋生態系評価論研究室 教授
1973年 広島大学水畜産学部水産学科卒業 2012年8月30日掲載 |
||||||
| 脚注
|
||||||
| 1. | 「海洋立国推進功労者表彰」(首相官邸ホームページ) |