
|
|||
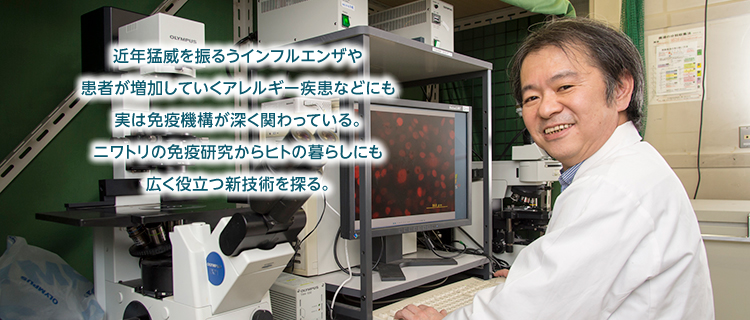 |
|||
 |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
 |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
 |
|||
|
|||
| 堀内 浩幸 教授 | |||
| ホリウチ ヒロユキ 免疫生物学研究室 教授 1992年1月1日~2002年3月31日 広島大学総合科学部・生物生産学部 助手 2017年5月19日掲載 |
|||

|
|||
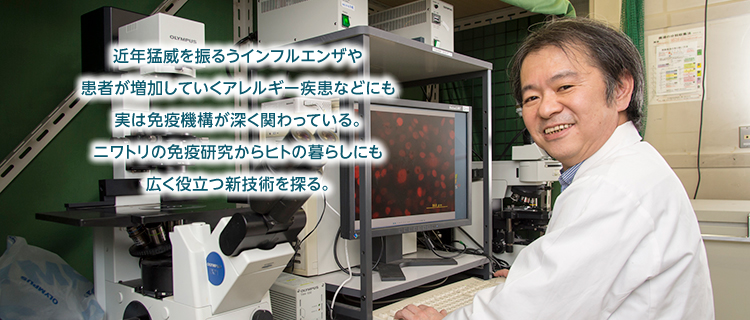 |
|||
 |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
 |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
 |
|||
|
|||
| 堀内 浩幸 教授 | |||
| ホリウチ ヒロユキ 免疫生物学研究室 教授 1992年1月1日~2002年3月31日 広島大学総合科学部・生物生産学部 助手 2017年5月19日掲載 |
|||